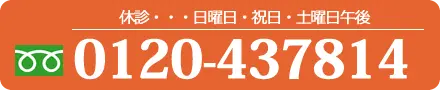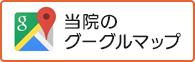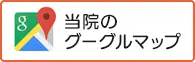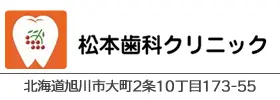旭川の歯医者 歯科医院開業25年の松本歯科クリニック
院長 松本弘幸
https://matsumoto118.com/
概要
小児矯正治療は、正しい時期に始めることが重要です。歯並びや顎の成長に影響を与えるため、適切な時期に治療を開始することで、将来の歯の健康や美しさをサポートできます。本記事では、小児矯正が可能な時期とその重要性について解説します。

目次
1. 小児矯正治療の基本とは
2. いつから小児矯正が可能か?
3. 早期治療のメリットとは?
4. 小児矯正の適切なタイミングとは?
5. 親が知っておきたい小児矯正のポイント
1. 小児矯正治療の基本とは
小児矯正治療は、子供の歯や顎の発育を監視し、不正咬合や歯並びの問題を早期に修正する治療法です。装置やブレースを使用して、歯や顎の位置を調整し、美しい笑顔や正しい噛み合わせを実現します。
歯並びは舌や唇の正しいサポートが必要なので、唇をポカンと開けていたり、舌が低い位置にあったり前に突き出す癖があると良くありません。
子どものうちから正しいお口周りの筋肉の使い方を習得する必要があります。
2. いつから小児矯正が可能か?
小児矯正治療は、一般的に乳歯が永久歯に生え変わる、8〜14歳の間に行われることが多いです。この時期に上下の歯の噛み合わせの関係や歯の生える位置がおかしいと、そのまま永久歯列になってしまい、自然と治ることはありません。ただ、反対咬合に関しては顎の成長に大きく関わってくるためより早期の対処が必要で、3歳半くらいから矯正治療の適応になります。
しかし、個々の症状や成長の段階によって対処法が異なりますので、歯科医師の診断と判断が必要です。
3. 早期治療のメリットとは?
早期治療は、歯や顎の成長段階で問題を修正することができるため、将来的な重篤な矯正治療を予防できる可能性があります。例えば顎の骨を切ってつなげ直すような外科矯正、あるいは小臼歯を抜歯する抜歯矯正などを避けることができる可能性が高くなるということです。また、顎の成長を誘導し、顔のバランスを整える効果もあります。
4. 小児矯正の適切なタイミングとは?
歯科医師は、子供の歯や顎の成長を定期的に評価し、適切なタイミングで治療を開始することが重要です。成長期に治療を行うことで、より効果的な結果が得られます。
永久歯列になると顎の骨が頑丈になり、歯を動かしにくくなりますので、通常は乳歯と永久歯が混在している時期が小児矯正に適切なタイミングです。
一方、反対咬合の矯正はその後の歯並びに大きな悪影響を及ぼすので、歯が生え変わり始める前(乳歯列騎)に小児矯正を始めたほうが良いでしょう。
5. 親が知っておきたい小児矯正のポイント
親は子供の歯の成長や歯並びに注意を払い、定期的な歯科検診を受けることが重要です。早期に歯並びの問題や不正咬合を発見し、歯科医師と相談することで、適切な治療を受けることができます。
歯並び以外にも、鼻で呼吸ができるか、口をポカンと開けていないか、指しゃぶりをしていないか、クチャクチャ音を立てて食べていないか、食べこぼしが多いかどうか、食べる時の姿勢はどうかを注意してください。大人と一緒の食卓で食べるときは足を床に接地させておくことが正しい姿勢の維持に大切で、サイズが合う踏み台を用意してください。
まとめ
小児矯正治療は、適切なタイミングで始めることが重要です。通常は8歳から14歳、反対咬合では3歳半からの早期治療をお勧めします。
また親は普段から子どもの食事や話し方、口の動かし方に注意を払い、定期的な歯科検診と早めの歯並び相談をしましょう。口周りの筋肉を正しく使えるように訓練することも必要です。
小児矯正治療を始める時期が遅いと、将来歯を失ったり大がかりな手術が必要になることもありますので注意してください。
旭川の歯医者 歯科医院開業25年の松本歯科クリニック
院長 松本弘幸
https://matsumoto118.com/