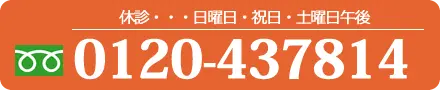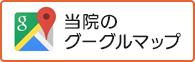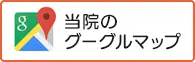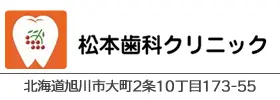はじめに
こんにちは。旭川市の歯医者、開院24年の松本歯科クリニック院長、松本弘幸です。
今回は、成人の90%が罹患しているといわれている歯周病治療・予防がなぜ必要か、お伝えしていきます。
歯周病治療は病状の進行を止め、歯と歯茎を守り、炎症症状を軽減する役割があります。歯周病予防は病気の進行を防ぎ、口腔全体の健康を維持するのに役立ちます。
歯周病が放置されると、歯を失う可能性や全身の健康にも影響を及ぼすリスクが高まることがあります。
定期的な歯科検診と適切な口腔ケアは、歯周病の早期発見と健康の継続的維持のためにとても大切です。

歯周病とは
歯周病は、歯と歯茎の周囲にある組織に炎症が生じる状態です。
初期段階では歯茎が腫れたり出血したりすることがありますが、進行すると歯茎が後退し、歯の支持組織が損傷を受けます。
この状態が放置されると、最終的に歯が失われる可能性が高まります。
歯周病の全身疾患との関係
歯周病は口腔だけでなく、全身の健康にも影響を及ぼすことが知られています。
歯周病の炎症性物質が体内に広がることで、心臓病、糖尿病、呼吸器疾患などのリスクが増加する可能性があります。
そのため、歯周病の予防と管理は、全身の健康を維持するためにも重要です。
歯周病予防の必要性
歯周病の予防には、日常的な口腔ケアが必要です。
適切な歯磨きやフロスの使用、定期的な歯科検診、専門家のアドバイスに従うことが大切です。
また、リスク要因となる喫煙やストレスの管理も考慮することが重要です。
歯周病予防・治療のポイント
1. 適切な口腔衛生 歯を磨くことやフロスを使用することで、歯と歯茎の周囲の細菌やプラークを除去します。
歯垢(プラーク)の蓄積が歯周病の原因となることが多いです。
2. 定期的な歯科検診 歯科医師の定期的なチェックアップによって、早期段階で歯周病の兆候を発見することが大切です。
早期発見することで病状の進行を防ぐことができます。
3. 専門的なクリーニング プロの歯科衛生士による専門的なクリーニング(デンタルクリーニング)を受けることで、効果的に歯石や歯垢を除去できます。
4. 口腔ケアの指導 歯医者さんに適切な歯磨きやフロスの方法、マウスウォッシュの使用方法などの指導を受けることで、自宅で効果的なセルフケアができるようになります。
5. リスクファクターの管理 喫煙やストレス、糖尿病などのリスクファクターが歯周病のリスクを高める可能性があるため、それらのリスクを減らすことができるかを検討してください。
6. 治療プランの選択 歯周病の進行度に応じて、歯周ポケットの清掃や歯茎の手術などの治療方法の説明を受け、これからの長い人生を快適に過ごすため最良の選択をしてください。
7. 食事と栄養 健康的な食事は口腔衛生環境にも影響を与えます。特に砂糖を過剰に摂取することは歯垢やむし歯、歯周病の原因になります。
バランスの取れた食事と水分摂取を心がけましょう。
8. ストレス管理 ストレスは免疫系や炎症に影響を与えることがあり、歯周病の進行を悪化させる可能性があります。
適切なストレス管理方法を見つけることが大切です。
9. 個別のケースに対応 患者さんごとの状態や健康状態に応じて、歯医者さんで最適な治療計画を立ててもらうとよいでしょう。
一人ひとりのニーズに合わせたケアを受けることができます。
10. 継続的なフォローアップ 歯周病の治療や予防は一度だけでなく、継続的なフォローアップを受けましょう。
患者さんそれぞれの歯周病の進行状況を定期的にモニタリングしてもらい、必要に応じて治療プランを立ててもらいましょう。
まとめ
歯周病予防・治療のポイント
セルフケアで適切な口腔衛生を保ち、食事と栄養に気をつけ、 ストレスなどのリスクファクターを適切に管理しましょう。
また歯科医院で定期的な歯科検診を受け、個別の治療プランを提示してもらい、口腔ケアの指導や専門的なクリーニングを受けましょう。
歯周病の治療や予防は一度だけでなく、継続的なフォローアップを受けましょう。
旭川市の歯医者 松本歯科クリニック
院長 松本弘幸